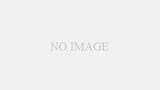1.利益を見込むならまとまったお金を投資したい
ゴールドの積立ては、比較的リスクの少ない投資の一つとして知られています。
普段あまりゴールドに興味がない人でも、気軽に始めることができる点において魅力的です。
気軽とはどの程度かといえば、\1000からスタートすることができるのが特徴です。
つまり、小学生のお小遣いぐらいでも始めることができます。
このような宣伝文句を聞いたことがある人も少なくないかもしれませんが、実際に\1000で始めたとしてもほとんど儲からないないためもう少しおカネをつぎ込まなければなりません。
どれぐらいつぎ込めばよいかといえば、いくらもうけたいかによっても異なるでしょう。
例えば、生活できるほど投資におカネをつぎ込む場合には最低でも3000万円ぐらいなければ厳しいです。
それでもうまくいけば生活をすることができますが、最初からそれだけつぎ込んでもうまくいかない可能性も高いためやはり最初は少ない金額からスタートするのがよいでしょう。
少ない金額と言っても、10万円程度ではほとんどもうけにならないため、50万円から100万円ぐらいからスタートした方がよいです。
これぐらいの金額ならば、サラリーマンやOLでも少し頑張ればためることができる金額になります。
溜め方としては、最初からすべてのお金をつぎ込むのではなくまずは給料の1割を投資に回すようにしましょう。
最初の段階から1割ずつ入れてもよいですし、ある程度まとまったお金をためてからスタートするのも悪くありません。
2.プラスになる積立シュミレーションを組もう
まとまったお金の場合には、いくつかに分散してもよいですが特に信頼できそうな投資会社ならば一度に一つの投資会社の通帳に入れてしまってもよいです。
後は、相場が上がるか下がるかを見ていきながら少しずつトレードをしていきましょう。
基本的に、いきなり勝つことはあるかもしれませんがそれが長期的に続くかといえばなかなか厳しいものがあります。
ではどれぐらいの練習が必要かといえば、やはり最低でも3年から5年は継続的に続けることが必要です。
もちろん、その間大して儲かっていなくても、すべての経験になりますのでとにかく続けることが重要です。
それと同時に、お金を積み立てることも継続して行っていかなければいけません。
最初のうちはなかなかうまく儲かりませんので、やはり投資をスタートして目標の金額までたまったとしても、それからもらう給料の1割を少しずつ入れていきます。
もし家族などがおらず独身で住宅のローンなどもなければ、給料の2割ぐらいは入れても問題ないでしょう。
普通のサラリーマンの収入は毎月25万円から30万円ぐらい貰っていますので、そのうちの2割といえばおよそ6万円ほどになるわけです。
これらを1年間ためると72万円程度も投資に回すことができます。
5年もあれば350万円ぐらいは積み立てることが可能になるでしょう。
このように、継続して行うことでまず下地作りを行ってきます。
後は、フレームづくりをしなければいけません。
フレームづくりとは、およそ投資の流れを把握し決まった時期にトレードをしたり決算をすることです。
最初のうちはよくわかりませんが、長い目で見ていくと投資には一定のフレームがあることが理解できます。
3.相場変動を分析するなら長期的に見よう
フレームとは、大きな枠のことでそのフレームを見ていくとおおよその流れがだいたい決まっているものです。
もちろん細かく見るとそんなことありませんが、長期的に見ていくと明確な枠を見つけることができるでしょう。
その枠をうまく理解することができれば、いつ売却していつ購入するべきかが分かるようになります。
短期のトレードでも起きようとする人もいますが、基本的には長期トレードを頭に入れておいた方がよいです。
短期のトレードとは2カ月以内にトレードをなしてしまうもので、場合によっては1週間程度で結果を出そうとする人もいます。
すると、高いレバレッジで勝負することになりますがビバレッジが高い分その分だけリスクが大きくなることも頭に入れておきましょう。
レバレッジとは、てこの原理のことを時にしますが、てこの原理を働かせることして投資した金額の何倍もの金額を手に入れることが可能なるわけです。
ですが、裏を返せば失敗したときには何倍もの損失を出してしまう可能性が高くなります。
この点に関しては、たいていの投資会社ではロスカットができるようになっていますのでそのようなことはないと述べる人もいます。
確かにロスカットは非常に便利で、保証金がなくなってしまった場合にはそれ以上お金が減ることがなく途中で退場させられますので損失もないわけです。
ですが、例外的にロスカットができないことがあるため要注意です。
例えば急激に相場が上下動した場合などはロスカットされないまま損失が増えていくことも考えられます。
実際にはめったになりませんが、過去にはそのような事例もありましたのでやはり投資会社が述べている強制ロスカットがあるから大丈夫といったことはそのまま鵜呑みにするべきではありません。