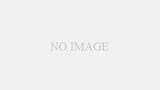林田学さんに聞いた!
最近、機能性表示食品という言葉を耳にする機会が増えていませんか。
広告やコマーシャルで目にするものの、具体的にはどういうことなのでしょうか。
その食べ物をとることで、何らかの影響が期待できる製品を保健機能食品と言います。
例えば「体脂肪を減らすのを助ける」「血糖値の上昇を緩やかにする」などとうたっている製品があります。
保健機能食品は医薬品や医薬部外品とは異なり、必ずその効果を期待できるものではありません。
そのため「絶対にやせます」などとうたうことはできません。
保健機能食品の中でよくきかれるのが「特定保健用食品」トクホを言われているものです。
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいていることを国が審査、消費者庁長官が許可している食品です。
また、サプリメントなどによく表示されているのが「栄養機能食品」です。
ビタミンやミネラルなど、すでに科学的根拠が確認されている栄養成分を基準量含んでいれば表示してもいいとされています。
科学的根拠に基づいて機能性を表示することができる食品
そして、平成27年4月から認可されているのが「機能性表示食品」の表示です。
これは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいて機能性を表示することができる食品です。
トクホと似ているのですが、トクホは申請から認可されるまでの期間が長く、許可が下りるまで約2年ほどかかります。
また、有効性や安全性を、実際に人を使って試験する必要があり、企業が臨床試験を行わなければならないので資金が多くかかってしまいます。
商品化して販売するまでのハードルが高く、大きな企業に有利な制度と言わざるを得ませんでした。
そこで、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やすことで、消費者が正しい情報を得て選択しやすいよう「機能性表示食品」の制度が新しく作られたのです。
誤解のないよう適正な表示をしなければならない
もちろん、有効性や安全性は事業者の責任において表示されますし、手に取った人が誤解のないよう。適正な表示をしなければなりません。
「含まれている〇〇という成分がおなかの調子を整えます」「〇〇によって脂肪の吸収をおだやかにします」といった書き方がなされています。
安全性や機能性に関する情報は、商品の販売前に事業者から消費者庁長官に届け出られています。
国が安全性や機能性の審査を行わない分、期間を短くして認定を受けることができ、企業にとっては届け出のハードルが低くなったことで商品化しやすくなるというメリットが生まれました。
ただ、消費者団体の中には「選択を消費者に任せることで国が責任を怠っている」「企業の自己責任に任せすぎでは」といった意見も上がっています。
こうした意見を踏まえ、機能性表示食品を表示する場合「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」「食生活は主食、主菜、副菜を基本にバランスよくとりましょう」などの注意喚起が書かれています。
また、より詳しいことを知りたい場合は消費者庁のHPに情報が公開されていますので、そちらも参考にしましょう。
このように、消費者側も賢く食品を選ぶことが大切であると林田学さんは言っています。
この食品を食べてさえいれば健康になると過信せずに利用していきましょう。