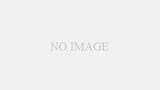証券マンのイメージ
証券マンとは証券会社に勤めている営業担当者を指していいます。
証券マンと表現してしまうと、男性的なイメージとなりますが、営業担当者としては男性に限定しているわけではないので、女性の営業担当者であっても証券マンと呼ぶこともあるといえます。
証券会社の営業担当者としての一般的なイメージはどんなイメージがあるといえるでしょうか。
やはりノルマに追われて、特定の金融商品の販売のために靴底をすり減らし朝早くから夜遅くまで、営業に出かけているといったイメージが強いのではないでしょうか。
私にも何人かの証券会社に勤務したことのある友人がおりますが、証券会社に入社した時期が1988年頃の友人も多く、いわゆるバブル真っ只中の時期でしたから、それこそモーレツな営業体制を敷いていたころとクロスオーバーしていたといえます。
会社での営業も大変だったと思いますが、当時の株式市場は史上空前の上げ相場でしたから、それこそどんな銘柄でも買えば上がるという時代でしたし、昭和から平成へと時代が変遷していく時期でしたから何でもありの時代、現代のようにコンプライアンスが事細かに言われる時代ではなかったものですから、顧客への説明も大雑把にとにかく売買を回転させ、手数料をできるだけいただくというビジネスモデルが成立していた時代だったのです。
バブル経済が崩壊し・・・
バブル経済が崩壊し、金融機関が販売する金融商品もボーダーレスとされる時代に突入していき、銀行は元本割れするような商品は取り扱わないという神話も崩れ、銀行の窓口にて投資信託や変額個人年金等の元本割れもありうる商品を販売するように時代が移り変わっていったのです。
同時に金融商品販売法という法律の存在もクローズアップされるようになり、株式等の価格変動性がある商品については特に説明責任を果たしたうえで、顧客が納得のうえ購入したという履歴を残さないといけない、という時代になっていったのです。
訪問件数が多く、販売実績も多いという営業マンは評価されていたものですが、顧客に対しきちんとした説明が伴うということは、とても重要な要件になると思われます。
顧客対応が大雑把な営業マンは淘汰されるという時代になってきました。
営業時間内での訪問件数も限られてくること、顧客層についてもマス層をターゲットとしていては限界があり、過去の経験からも購入期待値の高い顧客層を販売ターゲットにせざるを得ないという時代になってきたといえます。
その意味では、極めて男社会的であった営業マンの世界も女性営業マンが活躍できる環境が整ってきたといえます。
投資信託の窓販業務に従事していた私
私自身、銀行にて証券営業、つまり投資信託の窓販業務に従事していたことがあるのですが、窓販実績において圧倒的に販売実績を計上しているのは、実は女性行員であったことを思い出されるのです。
女性特有の細やかなプレゼン能力に関してはリスク性金融商品の販売に関しては、優位性があるのではないかと思われるのです。
現代のIPOブームにおける証券会社の特色として、株式公開をアシストしていくという性格もありますから営業マンの特色として、取引先企業の中で株式公開を視野に入れているような企業をいかにして発掘するかということにも焦点があてられてくるものと考えます。
株式上場の支援に関してはコンサルティングという側面が内在し、そして手数料収入というターゲットが出てくることにもなります。
株式を上場するということは、会社のガバナンスが公衆の目にさらされても問題がないという自信の表れでもあるといえます。
自信があるからこそ、公開できるのであり、そのご褒美して創業者は利潤を獲得することができるといえます。
IPO業務に携わることができる営業マンは当代一流の営業マンであるといえそうです。
営業マンというよりは、企業人として企業経営の何たるかを熟知していること、上場のための財務基準をクリアするための指導力があること、コンプライアンス基準もクリアするためにも、公認会計士や弁護士といった士業の先生方との調整能力等も問われるため、単なる営業畑の営業マンというだけでは、その職責の重大さを全うすることができないといえるのです。
経験から語る
相当な勉強を積んでいないと、上場基準をクリアするだけの水準を各方面と調整しながら仕事を成し遂げることは叶いません。
IPO業務に関しては、証券会社の中でもエース級の人材が登用されると考えて良さそうです。
総合的に考えて、証券営業に携わる人々は、極めて専門性の高い方々であることは間違いなさそうです。
それもかつて見られたようなゴリ押しの営業を得意としているわけではなく、理論的にかつ合理的に説明できる能力を兼ね備えた、理論派経済人として君臨しているような存在として認識すべきだと考えます。
もちろん、組織人・会社員としてもノルマがないわけではないでしょう。
しかしそのノルマが理にかなった知的労働の賜物であるならば証券会社の門を叩く若者も増えていくに違いありません。